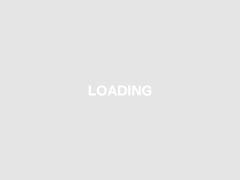イベント
ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]
ゲーム開発において,いいシナリオを作りたいと思いつつ,物語や設定をどうするか,というのは,多くの人がぶつかる課題だ。物語や設定が持つ役割を分析しながら,ロジカルに制作する手法を紹介したい。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/003.jpg) |
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/002.jpg) |
講演者は,ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンでシニア・アドボケイトを務める𥱋瀨洋平氏。
講演の内容は,シナリオ制作に興味のある小規模開発向けの初心者講座だ。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/004.jpg) |
「予想外」は,予想させることから始まる
講演の冒頭では,𥱋瀨氏の経歴や研究分野の紹介が行われた。1995年の大学入学以降,さまざまなゲーム会社でゲームデザイナーおよびシナリオライターなどで携わる。参加した主なプロジェクトは,「ワンダと巨像」「グローランサー」「魔人と失われた王国」などだ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/005.jpg) |
𥱋瀨氏のプロフィールサイト
2012年からは大学などで教育方面にも力を入れながら,研究者として活動している。この研究分野が,本講演の主題である「ゲームの物語や設定の作り方」に関わってくる。
情報工学を活用したゲーミフィケーション分野の研究が主に紹介され,シームレスに難度を調整することで誰でも神プレイができるアクションゲームや,学会参加者140人で協力して強力なボスに挑むゲームなどを開発している。
後者では,学会では知っている人同士で話すことが多いため,知らない人に話しかけるきっかけをゲームシステムで作り出した例だ。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/007.jpg) |
[CEDEC 2015]「誰でも神プレイできるジャンプアクションゲーム」を通じて得られた「上達するための経験」とは
![[CEDEC 2015]「誰でも神プレイできるジャンプアクションゲーム」を通じて得られた「上達するための経験」とは](/games/999/G999905/20150831094/TN/010.jpg)
CEDEC 2015のインタラクティブセッションでは,昨年の「誰でも神プレイできるシューティングゲーム」に続き,「誰でも神プレイできるジャンプアクションゲーム」が展示されていた。なるほど,前年と同じくプレイヤーの入力を自動的に補正してくれるゲームデザインが――と思いきや,そこにはちょっと意外なデータが示されていたのでレポートしたい。
VR分野では,ドローンや気球で撮影した映像を利用し,現実世界でジャンプすると,ものすごい高度まで飛ぶ疑似体験ができる「Hiyoshi Jump」や,人間の空間知覚をコントロールして,実際は曲がって進んでいるのにまっすぐ進んでいると感じさせる技術デモ「Unlimited Corridor」なども紹介された。
Unlimited Corridorは,2017年の「第20回 文化庁メディア芸術祭」のエンターテインメント部門優秀賞を受賞している。同部門の大賞は映画「シン・ゴジラ」が獲得しており,物語の力には敵わず,ゴジラに倒されましたと冗談をこぼしていた。
実績として紹介されたものは,一見するとどれも物語に関係なさそうだが,𥱋瀨氏曰く,これらのプロジェクトに共通する「体験を作る」ということこそが,ゲームの物語とは何か,という話につながる。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/010.jpg) |
人間は,自身で体験した現象を時系列でつなげて,物語を作り出していくという。情報を得て,次にこういうことが起こる,というのを理解するプロセスだ。
この体験について,ゲームでは,「想像通りになること」と「想像通りにならないこと」を組み合わせることが重要になる。
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/011.jpg) |
𥱋瀨氏は,ゲームは想像通りにならないことが面白いとしつつ,それには,積み重ねが欠かせないとした。
予想がまったくできない唐突な展開ばかりでは,人間は予想をやめてしまう。予想の裏切りは,予想させた状態ではじめて成立するのだ。
そのため,ゲームの中で一貫した法則を作ったり,グラフィックスで「こうなるだろう」という期待感を提示したりする。
敵を踏めば倒せるというのを理解させた状態で,背中にトゲがある敵を出せば,トゲがあって倒せないだろうということが予想できる。このように,絶え間なく予想させて,それを裏切るというプロセスが大切となる。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/012.jpg) |
シナリオも同様に,ゲームプレイとは別の場所で,興味を持続させたり,予想外のことを起こしたりできる。ゲームシステムとシナリオの2つの軸が,複雑な体験を作り出すのだ。
そもそもゲームに物語は「必要」か
𥱋瀨氏は,ゲームにおいて「物語が本当に必要か」という問いかけをした。必要であることは,みんな分かりきっているだろうとしつつ,あえて問い直すことで,必要である理屈をしっかりと作って納得するというプロセスだそうだ。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/014.jpg) |
問いに対し,「ウェイソン選択課題」という論理問題が例に挙げられた。多くの人が直感的に誤答を選びやすいのだが,理由付けを行うと正答率が上がるというものだ。
下記に詳しい解説を示す。
・アルファベットの裏側には,数字が書かれている。
・このとき,以下のカードで「片面がDならば片面は3である」ことが正しいと確認するために,めくる必要があるカードを示せ。
※めくる枚数に制限はない。4枚それぞれで「めくる」「めくらない」を回答するイメージ
この問題をじっくりと考えずに解いた場合,「D」と「3」をめくる人が多いと言われている。「Dなら3」「3ならD」というのを確認しようとするのだ。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/015.jpg) |
しかし,正解は「D」と「7」である。
条件:「片面がDならば片面は3である」
・「D」について
裏面に書かれたのが「3」なら,条件に一致する
裏面に書かれたのが「3以外」なら,条件に反する
→「3」と「3以外」の場合で,条件を満たすかが変わるので,めくる必要がある
・「K」について
裏面に書かれたのが「3」でも「3以外」でも,条件の検証に関係しない
→「3」でも「3以外」でも条件の反例になりえないため,めくる必要はない
・「3」について
裏面に書かれたのが「D」なら,条件に一致する
裏面に書かれたのが「D以外」なら,条件の検証に関係しない
→「D」でも「D以外」でも条件の反例になりえないため,めくる必要はない
・「7」について
裏面に書かれたのが「D」なら,条件に反する
裏面に書かれたのが「D以外」なら,条件の検証に関係しない
→「D」と「D以外」の場合で,条件を満たすかが変わるので,めくる必要がある
この問題で興味深いのが,理由付けを行うことで,正答率が向上するという点だ。
例えば,アルファベットを年齢に,数字を飲み物に置き換える。
「19歳」「22歳」の裏面(飲み物)が不明で,「お茶」「ビール」の裏面(年齢)が分からない状況で,飲酒していいのは20歳からという条件にする。
こうすると,多くの人が正しく「19歳」と「ビール」をめくるようになる。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/016.jpg) |
要は,「Dならば,3である」という抽象的な条件を「未成年(19歳以下)ならば,お茶である」という日常的な条件に変えただけだ。
前者では,直感的に「D」と「3」をめくりたくなるのだが,後者では,未成年にビールを飲ませる訳にはいかないので,ビールの裏面(飲む人の年齢)を確認することになる。
𥱋瀨氏は,論理的には同じ問題でも,日常的で答えやすい形にすると,人間の脳が正しく働くと指摘した。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/017.jpg) |
ゲームは,戦いやスポーツなどを,プログラミングで実装するために,すべて数式にする必要がある。
極論,ゲームというのは,数字のリソースをやり取りしているだけだ。だが,このやり取りだけをみても何も分からない。
これに絵が付いて,我々が日常的に体験するようなものに変換することで,プレイヤーは,素直にゲームシステムを理解できる。ゲームに物語があったほうがいい理由はいろいろとあるとしつつ,これこそが,ゲームに物語が必要な理由の大きな部分となると,𥱋瀨氏は続けた。
ゲームのシナリオをロジカルに作成する
ゲームにおける物語の重要性を確認したところで,具体的な物語の作り方について解説が行われた。
𥱋瀨氏はこれまでシミュレーションRPGを中心に手がけてきた経験から,SRPGにおける物語の役割は,戦う理由を説明するためのものだ,と説明した。
ただし,単に,「戦ってほしい」と言われても,人間は反発してしまうという。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/020.jpg) |
この反発には,「心理的リアクタンス」が関係している。
心理的リアクタンスとは,人が自身の自由な行動が制限されたり,奪われたりしたと感じたときに,その自由を回復しようとする心理的な抵抗や反発のこと。命令されるなどして,ほかのことができない状況に陥ると,人は強いストレスを感じる。
例えば「宿題をしなさい」と,言われると,本当に今から宿題をやろうと思っていたとしても,自由を制限されたことへの反発から,逆にやらない選択を取ってしまうというのが身近な状況だ。
そのため,プレイヤーが自身で考え,行動を選択したと思えるシチュエーションが必要である。
つまり,戦いたくなるような状況や背景設定を用意して,プレイヤーが自発的に戦いに出る動機を付けることが重要なのだ。
「ドラゴンクエスト」などを例にすると,平和を取り戻すために,勇者の末裔である主人公が村を出て冒険に出る,というイメージだ。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/019.jpg) |
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/022.jpg) |
最初こそ物語的な理由で主人公が外に出るが,だんだんプレイヤーは,戦闘や探索そのものを楽しむようになるので,そうなったところで,船を渡して世界を自由に冒険できる状況にしていると,𥱋瀨氏は分析していた。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/021.jpg) |
この背景設定に必要なのは,忠実なリアリティよりも納得感だ。
「インディ・ジョーンズ」のような遺跡を探索するゲームでは,宝を手に入れるためには遺跡を調査する必要がある。
遺跡にはトラップが張り巡らされており,それを突破しなければならない,という設定も,創作の世界ではあるあるなので,プレイヤーは受け入れやすい。
テンプレートを利用した物語制作
そのほか,「命の危機が迫っている」「失ったものを取り戻す」「復讐に向かう」など,主人公が行動を起こすきっかけの分かりやすい理由というものは,さまざまなものがある。
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/025.jpg) |
多くの物語には共通項があり,それがテンプレートとして,分析できるものとなっている。古典的研究として,ロシアの昔話を研究し,登場人物たちの行動を整理したウラジミール・プロップ氏の「昔話の形態学」が紹介された。
![画像ギャラリー No.026のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/026.jpg) |
これらの基本的な構造としては,プレイヤーキャラクターが「目的」のために,「ゲームのメインアクション」をするというものだ。
この目的について重要となるのが,キャラクターにも人格があるので,大きな目的とは別に「個人的な動機」も用意することである。
個人的な動機というのは,「英雄の子孫であり,魔王を倒しに行く」という目的を抱えた主人公は「英雄の子孫ではなく自分自身を見てほしい」という動機があったり,「廃部の危機にあるサッカー部を救う」という目的で入部した主人公は「マネージャーにモテたい」という動機だったり,といった具合だ。
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/029.jpg) |
しかし,この個人的な動機は,基本的に満たされず,むしろ反対の結果を招くことになる。個人的な動機が満たされてしまえば,大きな目的に向かう必要がなくなるからだ。
先ほどの例では,英雄としての名声が高まっていったが,むしろ重圧に苦しむことになったり,マネージャーのことを知れば知るほど,自分のことが眼中にないと気づいたり,という展開になる。
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/031.jpg) |
挫折などを経て,個人的な動機は弱くなっていくが,より大きな目的に目覚めていく。真の英雄を目指す,サッカーそのものへ情熱を注いでいく,といったイメージだ。
こうした展開は,広く受け入れられやすく,王道の物語として定着している。
物語の序盤・中盤・終盤の作り方
物語の導入については,どうすればいいか迷う人が多いことに触れながら,まずは,日常を壊すシーンから始めることが推奨された。
人は安定した状態だと,チャレンジを行わない。だからこそ,物語の導入は,日常を壊すシーンから始まることが多い。
故郷の村が襲われたり,記憶喪失や異世界転生といった設定が用いられたりする。これらは,プレイヤーと主人公の感覚を一致させやすい。
![画像ギャラリー No.050のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/050.jpg) |
主人公が主人公たる理由も重要だ。英雄の血筋だったり,相対的に優れていたり,そもそも唯一の生き残りでほかにいないといった状況を作ることで,プレイヤーにも納得感を与えられる。
![画像ギャラリー No.051のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/051.jpg) |
中盤では,ゲーム難度の上昇と物語を連動させることが重要となる。強敵が現れる場合でも,主人公たちの油断や,敵国の策略による包囲など,物語的なフォローを入れることで,納得感が生まれる。
![画像ギャラリー No.053のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/053.jpg) |
また,𥱋瀨氏は,主人公が一時的に能力を失う展開や,仲間を失うなど,壁にぶつかるシーンを入れることも推奨した。
プレイヤーを導いてくれたキャラクターが急にいなくなる展開は,急にいなくなることで,不便さだけでなく,寂しさも与えられる。
プレイヤーは,ゲームのシステム的な部分は変わらないものだと認識しているので,システムに影響を及ぼすような物語展開は,予想を効果的に裏切れるそうだ。
![画像ギャラリー No.054のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/054.jpg) |
終盤では,物語の前提を覆すというアプローチも有効だが,プレイヤーがこれまでやってきたことを全否定しない工夫が求められる。
魔王を倒すために冒険を続けていたのに,実は魔王が悪いわけじゃなかった,というような展開では,これまでプレイヤーがやってきたことが無駄に思えてしまう。
![画像ギャラリー No.065のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/065.jpg) |
また,𥱋瀨氏は,ラスボス戦の直前でゲームをやめてしまうというプレイヤーもいることを指摘した。ラスボスは,非常に強力で,倒すのに手間がかかる存在だ。
そのうえで,倒せば確実に世界が平和になるということが分かっていると,ゲームを進める動機が失われてしまう。ここで「ボスを倒したら仲間が消えてしまうかもしれない」といった不確定要素を加えることで,最後までの緊張感を保てるという。
![画像ギャラリー No.032のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/032.jpg) |
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/033.jpg) |
𥱋瀨氏によると,シナリオライターは意地悪なので,クライマックスまでに2,3人キャラクターが死ぬ展開を入れておくと,「どうせ助かるんでしょ」というプレイヤーの先入観を崩し,「このゲームは本当に人が死ぬから,これは助からないんじゃ」と思わせてくるんだ,と冗談混じりに言っていた。
物語における伏線についての考え方も紹介された。𥱋瀨氏曰く,伏線は「作るもの」ではなく,あとから見返して「見いだすもの」だそうだ。
物語を大きく展開したいときに,今まで書いたものを見返すと,言うだけ言って回収されていないものが見つかる。
これを回収することで,物語に説得力を持たせられるし,プレイヤーも「ここが伏線でつながるんだ」,と盛り上がるので,一石二鳥である。
結末については,一転して,「やりたいようにやろう」と強調した。ものすごく悪いことをしたのに完全におとがめなし,というような納得感のないものは共感を得られにくいというようなことはあるが,基本的に自分のセンスを信じて,表現したいものを描くべきとのこと。
![画像ギャラリー No.055のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/055.jpg) |
小規模ほど,制作者のセンスが好きで買うという人が多いので,売れるにはどういう結末がいいか,ということを考える必要はない。むしろ自由に書いたほうが作品の魅力が際立つ。
大前提として,物語を最後まで楽しんでもらうには,ゲームを最後までプレイしてもらう必要がある。プレイヤーが途中で脱落しないように,シナリオで誘導しつつ,最後まで遊んでもらえるゲームを作るのが大事とのことだ。
![画像ギャラリー No.056のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/056.jpg) |
![画像ギャラリー No.057のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/057.jpg) |
![画像ギャラリー No.058のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/058.jpg) |
ゲームジャムでの実践例
講演では,ゲームジャムでの実践例も解説された。Unity 1週間ゲームジャムのお題「ない」で𥱋瀨氏が4日間(約30時間)で制作した「NA:I」は,数字だけを使った推理ゲームだ。
もともと,ADVを作りたかったが,絵が描けないので,数字なら書かなくていい,というアイデアから生まれ,数字の約数などの特性を使ったパズルに,キャラクター性を持たせた内容となっている。
![画像ギャラリー No.066のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/066.jpg) |
unityroom「NA:I」
中身としては,数字のロジックパズルのようなものとしつつ,話し方や関係性を推測させることで,プレイヤーが勝手にキャラクターの人格や背景情報を想像してくれるそうだ。
この意図的に情報を欠落させるアプローチは,逆にプレイヤーの想像力を刺激して,楽しんでもらえるという。
![画像ギャラリー No.035のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/035.jpg) |
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/036.jpg) |
また,𥱋瀨氏は,Global Game Jam 2025(GGJ2025)で「Bubbles」(バブル)というお題から,潜水艦を防衛するゲーム「The Bubble Diver: Submarine Defender」を制作した。
![画像ギャラリー No.037のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/037.jpg) |
最初は,「感情の泡で皆をハッピーにするゲーム」「五線譜の上に泡の音色が浮かび上がるゲーム」などといったアイデアもあったそうだが,制作時間などの都合上(GGJ2025には,Unityのサポートスタッフとして参加しており,制作時間は48時間のさらに一部),「泡を打ち上げるゲーム」に絞り込んだという。
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/038.jpg) |
アイデアの中でどれが面白そうか,と聞くと,感情の泡のアイデアを面白いと答える人が多いそうだが,これはそれぞれが想像しているものが違うためだからという。
何となくのイメージはあっても,それをゲームシステムとして成立させるのは難しい,と,𥱋瀨氏は振り返った。
その後,プレイヤーが泡を打ち上げるというアイデアのゲームデザインに進む。単に,泡で自分を守るとしたら,一か所で泡を打ち上げるだけの簡単なゲームになってしまう。
![画像ギャラリー No.040のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/040.jpg) |
そこで,イルカを主人公にして,泡で巣を守ることにしたが,イルカのイラストが大変なので,潜水艦が基地を守るという設定に変更した。
![画像ギャラリー No.042のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/042.jpg) |
![画像ギャラリー No.044のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/044.jpg) |
しかし,基地は絶対に動かないものなので,いつまで守ればいいのか,という問題が発生した。この問題を解決するために,潜水艦を座礁させて,潜水艦の修理が終わるまで守るという設定にしたそうだ。
![画像ギャラリー No.045のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/045.jpg) |
これにより,修理が完了すれば脱出という演出につながり,納得できる設定が生まれた。また,潜水士は,潜水艦を守る方法として泡を使う。
この泡を出すには,自身の酸素を使うので,大きな泡で守ろうとすると,酸素を大きく消費するというジレンマの体験につながったそうだ。
![画像ギャラリー No.046のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/046.jpg) |
unityroom「The Bubble Diver: Submarine Defender」
実際に個人や小規模でゲームを制作するときは,自分が作れるゲームシステムの延長で,どんなものが作れるかを考えることが多い。
しかし,ゲームジャムでは,普段まったく考えていなかったテーマから制作を開始するので,いい訓練になるという。
![画像ギャラリー No.047のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/047.jpg) |
仕事でのゲーム制作では,IPを原作とするタイトルなど,すでに確立されたキャラクターをベースにゲームを作っていく場面もある。原作で語られそうなエピソードに加え,原作者が作りそうなものを求められるという。
ここで𥱋瀨氏は,カイロソフトの「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」を,ここ1,2年で登場したキャラクターゲームの中で,屈指の完成度を見せるタイトルの1つだと紹介した。
カイロソフト定番で,誰にでも分かるゲームシステムを継承しつつ,ドラえもんファンが喜ぶストーリーを融合させている。さらに,「稀に見る藤子・F・不二雄ファンがスタッフにいると一目で分かるほどマニアック」と,その作り込みについても評価ポイントだと説明していた。
![画像ギャラリー No.049のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/049.jpg) |
ゲームは,テーマや自分がやりたいジャンル,キャラクターなどを,自分たちが持っている技術的にどう入れ込むか,というのをベースに構築していく。その体験を設計していく中で,物語も設計されているそうだ。
既存の仕組みに自分なりの設定を付けてみる
ゲーム体験において,シナリオは重要な役割を持つが,シナリオがないものに,設定を追加するだけでも,かなり面白くなるようだ。
𥱋瀨氏は,人狼ゲームの設定を変えてみることを,物語の作り方の訓練として推奨した。実際にやってみて一番盛り上がったのは,「研究者人狼」らしい。
![画像ギャラリー No.060のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/060.jpg) |
![画像ギャラリー No.061のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/061.jpg) |
ここは研究者たちがいる学会で,査読者が毎晩1人の論文を読み,リジェクト(拒否・差し戻し)していく。論文がリジェクトされた研究者はショックで学会を去ってしまう,というものだ。
学会などで論文提出したことのある人を始めとして,刺さる人には,かなり刺さる内容で,会場でも笑いが起こっていた。
ルールは変えず,設定を置き換えただけというのに,かなり興味をそそられる。これを例に,𥱋瀨氏は,ゲームの物語で戦う理由や乗り越えなければならないハードルを独自に説明するのは必須だが,非常に凝った内容にする必要はなく,よくあるものから,しっかりと作り込むと良いとした。
一度作ってしまえば,ゲームの盛り上がりとストーリーの盛り上がりを一致させたり,内容をひねったりもできる。
やはり重要なのは,先を読ませるということで,複雑な内容で先の展開が読めなすぎると,そもそも予測を諦めてしまい,響かないものになってしまう。
また,制作ではとりあえず手を動かしてみて欲しいと続けた。こういう物語を作ろう,といったとき,まずは叩き台を作ることが重要という。
叩き台の名の通り,チームから叩かれるかもしれないが,その書いた叩き台がなければ,そもそも制作の話が進まないのだ。
最後に𥱋瀨氏は,「初心者というのは,最初の志を胸に抱き続ける人のことだ」とし,ずっと初心者でいいので,やりたいと思ったことを続けていってほしい,と来場者たちにエールを送った。
![画像ギャラリー No.062のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/062.jpg) |
![画像ギャラリー No.064のサムネイル画像 / ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/064.jpg) |
𥱋瀨氏のプロフィールサイト
「ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン」公式サイト
「ゲームメーカーズスクランブル2025」情報ページ
- 関連タイトル:
 開発/テクノロジ
開発/テクノロジ - この記事のURL:


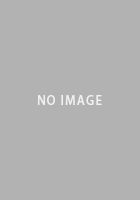
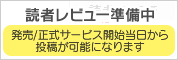
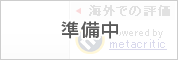






![ゲームにそもそも物語や設定は必要か。制作サイドから見る物語の役割と,ロジカルな初心者向け制作手法[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250902001/TN/067.jpg)