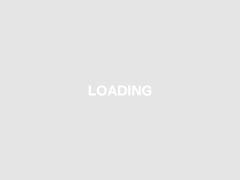イベント
効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/002.jpg) |
講演は,個人や小規模のゲーム開発者向けに,ゲーム制作におけるサウンドデザインの初めの1歩を踏み出すきっかけとなるものだ。倉持氏がこれまで業務で培ったサウンドデザインのノウハウや,友人と趣味で制作しているゲームのサウンドデザインを行った実例などが語られた。
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/001.jpg) |
倉持氏は,2009年にバンダイナムコゲームス(現:バンダイナムコスタジオ)に新卒で入社して以来,コンソールやアーケード,モバイル,VRなどのタイトルに携わり,2021年と2022年には,同スタジオのサウンドクリエイター新人研修なども担当している。
そのほか,CEDECに複数回登壇し,文房具メーカー・コクヨのオウンドメディア「WORKSIGHT」の外部編集部員としても活動した経歴を持つ。
(CEDEC 2016)「サウンドクリエイター新人研修の改革」インストラクショナルデザインの活用
(CEDEC 2019)「ゲームのサウンド制御技術」を「インドアプレイグラウンドのサウンド演出」へ応用した事例 〜屋内・冒険の島ドコドコ / VS PARK(ニゲキル)のサウンド開発について〜
(CEDEC 2023)「XR技術」で「少し先の未来の暮らし」を検証。 「XR HOUSE 北品川長屋1930」で建築領域と共創した共同実証実験の開発と検証の報告
(CEDEC 2023)「サウンドクリエイター新人研修の改革」インストラクショナルデザインの活用
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/004.jpg) |
「ゲームサウンドデザイン」とは何か
倉持氏は,本公演におけるゲームサウンドデザインについて,プレイヤーに「何を感じさせたいか」「何をさせたいか」を出発点に,どんな音を,どのようなタイミングや条件で鳴らすかを設計することだ,と説明した。
言い換えると,状況に応じて,プレイヤーに与えたい効果を考え,狙い通りに機能する音や,その鳴らし方の設計のことである。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/009.jpg) |
ここで重要なのは,ゲーム体験をサウンド面から計画・設計することであり,それぞれの音を作るときは,その効果や機能を満たすために必要な音を作ることが重要であるとした。
ゲームサウンドが持つ3つの主な機能
ゲームサウンドには,さまざまな機能を付与できる。倉持氏は,その機能を分かりやすくするために,大きく3つのカテゴリ「情報を伝える」「感情に訴える」「感触を伝える」に分けて説明をした。
なお,1つの音は,このうちの1つに当てはまるという訳ではなく,基本的には1つの音が複数の機能を持っているという。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/010.jpg) |
倉持氏は,主な3つの機能それぞれについて,具体的なタイトルを例に紹介していった。
まずは,情報を伝える例だ。バトルロイヤルFPS「Apex Legends」は,ゲーム進行につれ,オレンジ色のダメージを受けるエリアの壁(リング)が迫ってくる。この壁が近いという情報をドローンのような音で伝えている。
倉持氏は,ドローンのような音を消した動画を比較用に用意し,音をなくすと緊迫感が薄まることを示した。
次に,感情に訴える例では,非対称ホラー「Dead by Daylight」を挙げた。サバイバー側のプレイシーンでは,心音や恐怖を煽る音楽により,プレイヤーに恐怖という感情を与えている。心音を消し,音楽を陽気なものに差し替えると,ほかの要素は同じでも恐怖が薄れる。
最後に,感触を伝える例では,「The Last of Us」の近接戦闘シーンが取り扱われた。パンチなどの打撃音が生々しく,痛みやパンチの重さという感触を音によってプレイヤーに伝えている。
サウンドのディテールが,この世界が実在するかのようなリアリティを生み出しており,パンチの音をコミカルなものに差し替えると,生々しい感触が失われ,世界観が台無しになってしまうことも示された。
ゲームサウンドは,プロトタイプ制作フェーズから
まず,ゲーム制作全体の流れは,どのようなゲームを作るか,という「企画」フェーズから始まる。次に,仮の素材を使って,ゲームの核となる遊びや仕組みを試作して,面白さや課題を確認,改善を繰り返す「プロトタイプ制作」フェーズ。
プロトタイプ制作フェーズが終わってから,完成を目指す「本制作」(量産)フェーズがスタートする。
ゲームサウンドは,これらのフェーズのうち,プロトタイプ制作から参加することが多いそうだ。
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/014.jpg) |
企画やほかの職種と方針をすり合わせて,サウンドが効果的に機能する設計を試行錯誤しながら実装でき,ゲーム体験の質を高められるので,プロトタイプ制作からゲームサウンドチームが参加することが望ましいとも,倉持氏は説明した。
量産段階でサウンドチームが入る場合,実現したいゲーム体験の方向性が共有されず,ただリストにそって音を作るだけの機械的な作業になりがちという問題も起こりやすいそうだ。
また,実際の業務では,プロトタイプ制作と本制作の境界というものは曖昧なことが多く,明確にフェーズが切り替わったと実感できることは少ないという。
作業を円滑に進めるために,早い段階から方向性をある程度固めていくことが重要で,それには,だいたい75点以上くらいの音を目指して,音をどんどん入れて,実際に鳴らしてみるのが良いそうだ。
ゲームサウンドの作り方の流れ
ゲームサウンド制作の流れは,サウンドコンセプトを立て,モックアップ(試作品)を作り,実装,ブラッシュアップというのが一例だ。
手順通りに進むのが理想だが,実際は試行錯誤の中で,行程を行き来することを繰り返すこともあるという。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/015.jpg) |
・サウンドコンセプトの立て方
まず,サウンドコンセプトの定義が行われた。本講演におけるサウンドコンセプトは,ゲームのコンセプトを音で具現化するために,ゲーム全体を通して,どんな世界を作るか,どんな音の印象をプレイヤーに与えたいか,ということを,一言で表した特徴や方針のことである。
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/017.jpg) |
つまり,ゲームコンセプトが前提にあるので,それを確認することは必須条件だ。制作済みのビジュアルがある場合は,それを確認することで,より世界に合ったサウンドコンセプトを立てられる。
サウンドコンセプトを立てることで,プレイヤーに体験させたい狙いを明確にして制作を進められるメリットがある。
アイデアを考える時に取捨選択の判断基準が持てるほか,アイデアの取捨選択の判断基準にしたり,チーム内での共通認識も持てたりする。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/018.jpg) |
コンセプトを立てるときは,まず,「リファレンス」(参考にする作品)探しからスタートすることが提案された。ゲームに限定する必要はなく,映画やアニメを参考にするのも良いという。
リファレンス探しのコツは,YouTubeで「ゲーム名+No Commentary」と検索することで,実況音声の入っていないプレイ動画を見つけられることもあると紹介された。
ここで気を付けなければならないのが,「この作品が人気だから,これにそっくりの音にすればよい」と誤解しないようにすることだ。オリジナリティーがなくなってしまうし,プレイヤーにもすぐに気づかれてしまう。
リファレンスはあくまで参考となる土台であり,そこから自分たちの作りたいゲームにあった音を作り出していくのが大事だという。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/020.jpg) |
倉持氏は,芸術家パブロ・ピカソの言葉「優れた芸術家は模倣し,偉大な芸術家は盗む」を引用し,好きな作品をそっくり真似するのではなく,良いところを盗むという心持ちで,さまざまな作品に触れてほしいとコメントした。
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/022.jpg) |
・サウンドコンセプトの立て方:実践例
サウンドコンセプトの立て方の具体的な実践例として,倉持氏の友人が趣味で制作中のゲームのサウンドデザインを進めたときの作業が紹介された。
まず,ゲームコンセプトとアートのコンセプトは下記の通り。
・協力型パーティーゲーム
・友達同士でわちゃわちゃ盛り上がれる
・ゲーム慣れしていない人も誘いやすいもの
・ポップかつシュールなファンタジー
・プレイヤーが操作するのは,マシュマロの妖精
・使用するアセットのイメージ「Platformer Deathrun - Low Poly 3D Models Pack」
![画像ギャラリー No.071のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/071.jpg) |
![画像ギャラリー No.072のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/072.jpg) |
![画像ギャラリー No.025のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/025.jpg) |
倉持氏が最初に見たゲーム画面は,音や背景などもなく,グレーボックスが置かれているもので,プレイヤーはブロックを積み重ねて上の段に行くということが分かる内容のものだったという。
![画像ギャラリー No.028のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/028.jpg) |
![画像ギャラリー No.029のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/029.jpg) |
ゲームコンセプトやゲームシステムなどの情報をもとに,サウンドリファレンスとして「Fall Guys」や「カービィのグルメフェス」を挙げ,これらの作品の音をメンバーに聞いてもらい,イメージに近いということで方向性を固めたという。
また,チーム制作では,イメージから遠い作品を挙げるのも方向性を固めるのに有効だという。
今回の場合は,「Party Animals」「Gang Beasts」は,かわいいキャラクターでパーティー要素もあるが,音の方向性は異なるということをチーム内で確認し,方向性の解像度を上げていったという。
![画像ギャラリー No.030のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/030.jpg) |
![画像ギャラリー No.031のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/031.jpg) |
そうして,Fall Guysやカービィのグルメフェスのわちゃわちゃ感や,かわいさを参考に,マシュマロの妖精という世界観を生かした楽しさを作りたいという方向性から,「ふわポップ×ドタバタファンタジー」というサウンドコンセプトが誕生した。
![画像ギャラリー No.033のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/033.jpg) |
ふわポップは,明るくて耳になじみやすい柔らかい音で,ドタバタファンタジーはシュールでコミカルな効果音である。
一見すると相反する要素だが,これらを融合させることで,ユニークな設定を生かした独自の世界観を構築する。
![画像ギャラリー No.034のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/034.jpg) |
また,狙いたい効果(外したくない効果)は,パーティーゲームらしく,子どもから大人まで楽しめる,にぎやかで笑える音世界とし,全体の音をかわいくてちょっと変なテイストで統一することを決定した。
・モックアップ(試作品)制作の流れ
倉持氏は,モックアップについて,実際に音を入れる前に,ゲーム動画に対して,音やボイスなどを仮当てした試作品であると定義した。
モックアップで実際のゲーム映像で音を鳴らしながら,雰囲気やゲーム性とかみ合っているかを確認できる。
![画像ギャラリー No.036のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/036.jpg) |
また,あくまで動画に対して音を仮当てするので,ゲームへの実装よりも手軽に試行錯誤を繰り返せるうえ,チームへの共有も行いやすい。さらに,頭の中でイメージしているだけでは思いつかないアイデアも出てくるという。
一方で,モックアップの制作にこだわりすぎると,作業効率的にゲームエンジンに実装したほうが良かったという場合も起こりうるので,「モックアップの完成品を作る」ことを目的にしないようにと注意を促していた。
モックアップを制作する手順は,下記の通り。
![画像ギャラリー No.038のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/038.jpg) |
1.ゲーム動画を用意する
Windowsなら「Xbox Game Bar」,Macなら「画面収録」など,標準で搭載されているツールもあるので,まずはこれらを利用する。
![画像ギャラリー No.039のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/039.jpg) |
2.必要な音を洗い出す
音の洗い出しとは,ゲームの内容を確認しながら,どんな音が必要で,それをどういったタイミングで鳴らすべきかを検討する作業だ。
とはいっても,モックアップ時点ですべての音を洗い出す必要はない。開発が進む中で必要な音も変化していくため,まずは,ゲーム動画に対して,必要な音を当てていくくらいの気持ちで行うことが推奨された。
倉持氏が音の洗い出しでよく使う手法の1つは,「REAPER」というDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション,音楽制作・編集ソフト)で,動画を見ながら,音を鳴らしたい箇所にマーカーを打っていくことだという。
![画像ギャラリー No.041のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/041.jpg) |
「REAPER」公式サイト
DAWソフトにはいくつか種類があるが,REAPERを選択した理由について倉持氏は,拡張性が高く,操作性をカスタマイズしやすいことや,大量のアセットを一括で書き出したいというゲーム制作のニーズを満たすことを挙げていた。
もちろんモックアップは,動画に音を付ける作業なので,動画編集ツールでも代用できる。
3.BGMやSEを用意する
洗い出した音のリストに沿って,イメージに合うBGMやSEを用意(制作 / 購入)する。
自前で曲や効果音をすべて自分で制作する人もいるが,自分ですべて制作しなければいけない,ということはない。商用利用可能なサービスを活用するのも有効な手段だ。
ボイスについても,自分で声をあてたり,友人などに依頼したりする方法に加え,音声合成ソフトを利用する方法などもある。
利用規約などは,別途確認してほしいとしながら,倉持氏は次のサイトをオススメとして紹介した。
まずは,商用利用可能な既存のデータを利用して,イメージを固めていく。その素材がイメージと合っていれば,本制作時に,差し替えずそのまま利用するという方法もある。
効果音など,音の素材は数が膨大になりやすい。通常のフォルダ管理では,作業効率に限界が生じる。
そこで,倉持氏は,「Soundly」のような効果音ライブラリ管理ツールを利用することを推奨した。
![画像ギャラリー No.074のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/074.jpg) |
「Soundly」公式サイト
Soundlyで,大量の効果音を1つのソフトで管理でき,高速な検索や視聴,書き出しなども可能で,簡単な波形編集も行える。お気に入り機能で,良いと思った音だけのリストを作ったりもできる。
一部機能に制限があるものの,フリープランも用意されている。
![画像ギャラリー No.073のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/073.jpg) |
また,いくつかの効果音をクラウドで提供しているので,そちらも聞いてみて,足りなかったらSoundly上で効果音を買い足すということも可能だ。
欲しい音の探し方
ゲームを制作しているとき,イメージに合う音を探す難しさに直面したという人も多いだろう。
講演終了後に,倉持氏へ音の探し方について聞いてみると,「音を表現する語彙を広げていく」というコツを紹介してくれた。
たとえば,爆発音が欲しい場合,「explosion」と検索して,見つかった音のファイル名などを見ると「boom」「blast」「destruction」といった,別の表現を見つけられる。これをもとに,さらに検索をかけていく流れだ。
検索サイトでは,ショッピングサイトのように,似た音をサジェストしてくれる機能もあるので,イメージに近い音を少しずつ掘り当てていくイメージである。
このほか,対話型AIを使って,別の表現を教えてもらうというのも手だそうだ。語彙を広げていくことで,少しずつ解像度が上がり,ほしい音にもたどり着きやすくなる。
4.ゲーム動画に音を付けてみる
音を洗い出し,必要な素材を用意したら,ゲーム動画にBGMやSEを付けてみて,雰囲気を確認する。この作業を経て,実装へと進む。
・実装する
雰囲気を確認したら,音をゲームエンジンに組み込む実装フェーズに進む。倉持氏は,ゲームエンジンへの組み込み方は,それぞれで異なるうえ,アップデートで方法が変わるため,各公式ドキュメントなどを参考にしてほしいと説明した。
一方で,ファイルを用意するときは,ひとまずデータ形式はWAV,サンプリングレートは48kHz,ビット深度は24bitというフォーマットにすることを推奨した。高品質な分,ファイル容量が大きいという欠点はあるが,これをベースに,必要に応じて圧縮していくのが望ましいという。
![画像ギャラリー No.051のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/051.jpg) |
ゲーム画面に実際に音を付けたら,雰囲気が合っているか,ほかの要素とのバランスはどうか,といったことを確認しながら,細かい調整(ブラッシュアップ)を繰り返していく。この作業が最終的なゲーム体験に直結する重要な作業だそうだ。
しかし,ゲームの仕様やバランスが変われば,音も作り直すこともある。そのため,1つの音にこだわりすぎず,サウンドコンセプトを象徴するような音を優先的に調整していくのがポイントだ。
![画像ギャラリー No.053のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/053.jpg) |
ブラッシュアップの繰り返しを,イテレーションを回すともいう。イテレーションを回す中で,イメージと合わなくなってきた音は,差し替えたり,調整を入れたりする。
大量の音を管理するために「サウンドリスト」を作ることも効果的だ。スプレッドシートで,音の機能や発生条件,制作状況や実装状況などを記録したもので,チームへの共有にも役立つ。
イテレーションを回す中で,不要になった音も「不要になった」情報を残すために,グレーアウトするなど,制作で利用した音のすべての情報がここに集まるイメージだ。
![画像ギャラリー No.054のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/054.jpg) |
サウンドリスト制作のコツは,検索性を良くすること。セルの結合は,使うとソート機能が使えなくなるので避ける,左端に項番を付ける「No.」列を作っておき,サウンドリストに追加した順番がわかるようにする,といったことが推奨された。
![画像ギャラリー No.055のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/055.jpg) |
サウンド実装前に知っておきたい用語
最後に,サウンド実装に関する基礎用語が紹介された。
・ワンショット / ループ
ゲームサウンドには,パンチやジャンプ,UIのクリックなどに合わせて,瞬間的に鳴らすものと,たき火や滝の音などといった環境音や,BGMなど,一定時間鳴り続ける音がある。前者を「ワンショット」,後者を「ループ」と呼ぶ。
![画像ギャラリー No.057のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/057.jpg) |
・2D音源 / 3D音源
また,音の鳴らし方も主に2つの種類「2D音源」と「3D音源」がある。
2D音源は,キャラクターがどこにいても同じように聞こえてくる音だ。UIのクリック音や,BGMなど,システム的な音が主に含まれる。
3D音源は,音の発生位置に応じて,音量や定位が変化する音だ。足音や銃声など,ゲーム空間の中に音の発生源があり,そこに近づくか,遠ざかるかでボリュームが変化する。
![画像ギャラリー No.058のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/058.jpg) |
・発音数の制御
ゲームの中で,同時に鳴る音の数を制限する仕組みというものがある。これを「発音数の制御」と呼ぶ。
先に鳴っている音を優先する方法を「先着優先」,逆を「後着優先」という。発音数の制御は,1人の村人から同時に複数のセリフ音源が鳴らないようにしたり,銃を連射したとき,音が大きくなりすぎるのを防ぐ役割がある。
![画像ギャラリー No.062のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/062.jpg) |
![画像ギャラリー No.064のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/064.jpg) |
・バスルーティング
さまざまな音を一括して管理する方法として,バスルーティングという仕組みがある。SEやBGM,ボイスなどといったバスを用意して,ここを通して音を鳴らすことで,音量を一括で管理するというものだ。
各バスをまとめるマスターバスを用意することで,全体のバランス調整も行える。普段ゲームをプレイするときに,設定画面で目にする「マスターボリューム」「BGM音量」「SE音量」などといった項目を実現するようなものだ。
![画像ギャラリー No.066のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/066.jpg) |
なお,複雑なサウンド制御が必要な場合は,「Wwise」「CRIWARE」といった専用のミドルウェアを使うのがオススメとのこと。小規模開発向けの無料プランも用意されているので,興味があれば,まずは触ってみることを推奨した。
![画像ギャラリー No.068のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/068.jpg) |
「Wwise」商品紹介ページ
「CRIWARE」公式サイト
まとめ
倉持氏は講演を振り返り,サウンドデザインで重要なことは,自分ですべての音を作るということではなく,音の素材を「どう使うか」だと述べた
音を用意したら,モックアップで方向性を確認し,ゲームの開発進捗全体を見ながら,ブラッシュアップを重ねていく。
重要なのは,設定したサウンドコンセプトを実現できているか,という点にこだわることだという。よりよいゲーム体験を提供するために,サウンドを設計し,それを考え,形にするのが,サウンドデザイナーの役割だ。
![画像ギャラリー No.069のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/069.jpg) |
講演で解説した段取りや制作ツールは,サウンドデザイナーが考えることを支援するものだという。
倉持氏は,ゲームを作ったあとに,もっとこうしたらよかった,と思ったことがある人もいるかも知れないと前置きし,「考える時間を増やすことによって,皆さんの才能からあふれ出てくるアイデアをより多くゲームに反映させてほしい」と,講演を締めた。
![画像ギャラリー No.070のサムネイル画像 / 効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/070.jpg) |
バンダイナムコスタジオ 公式サイト
「ゲームメーカーズスクランブル2025」情報ページ
- 関連タイトル:
 開発/テクノロジ
開発/テクノロジ - この記事のURL:


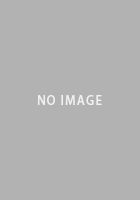
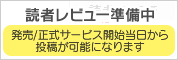
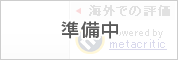






![効果音が変わるとゲーム体験も変わる。よりよい体験を提供するためのサウンドデザインの基礎と実践的なコツ[ゲームメーカーズスクランブル]](/games/991/G999101/20250904004/TN/075.jpg)