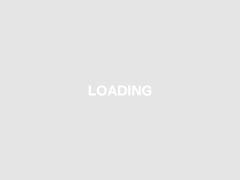イベント
AIを自分たちで作り,新たな産業を創出することが成長への道。さくらインターネットの田中邦裕氏による基調講演をレポート[CEDEC 2025]
3日間で約200ものセッションが予定されているが,そのトップを切ったのは,さくらインターネットの代表取締役社長を務める田中邦裕氏による基調講演「GX社会におけるデジタルインフラ進化論 〜クラウド×生成AI時代に、開発者が知っておくべき“基盤”の話〜」だ。
この講演では,さくらインターネットのこれまでの歩みや理念,低消費電力かつ再生可能エネルギーの利用を見据えて10年以上前に開設された,石狩データセンターの概要なども紹介されたが,それらは後日掲載の詳報に譲る。本稿では講演の後半に語られた,IT業界全体の視点から見たAI利用についての部分を主にレポートする。
※CEDEC運営事務局からの要請により,このレポートは講演の一部内容を省略したダイジェスト版となっている
![画像ギャラリー No.001のサムネイル画像 / AIを自分たちで作り,新たな産業を創出することが成長への道。さくらインターネットの田中邦裕氏による基調講演をレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250722034/TN/001.jpg) |
田中氏は,AIによって近年の社会が急速に変化していることに触れつつも,そういった技術革新による激しい社会変化は昔からあったと指摘した。その例として挙げたのが,1900年ごろからの十数年で,それまで街に溢れていた馬車が姿を消し,代わりに自動車が一気に普及したことだ。
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / AIを自分たちで作り,新たな産業を創出することが成長への道。さくらインターネットの田中邦裕氏による基調講演をレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250722034/TN/002.jpg) |
そして現在も,AIの進化によって社会は大きく変わろうとしている。田中氏は,資金調達額などのデータから「2022年からITはへこみ始めている」と表現し,AIがIT(≒Web)に変わる成長産業になると予測した。
といっても,Webが馬車のように姿を消すわけではない。Webはインフラ,つまり“前提”の存在となって,その上に載るAIが伸びていくという。
具体的には,何か知りたいことがあったときにGoogleで検索する(Googleの検索アルゴリズムを利用する)のではなく,AIチャットに聞くといった感じだ。これは単にGoogle検索が使われなくなる話だけに留まらない。例えば,これまでWeb関連のサービスで当たり前のように使われてきたSEO(検索エンジン最適化)も,AI相手では効率が落ちてしまう。
AIは,Webにあるデータを学習することによって,その精度を高めていく。田中氏も,WebがなければAIが成り立たないことは認識しているが,これからはWebにあるものを直接ではなく,AIによって利用する社会になっていくと予想した。
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / AIを自分たちで作り,新たな産業を創出することが成長への道。さくらインターネットの田中邦裕氏による基調講演をレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250722034/TN/003.jpg) |
では,そんな時代にどう対応していけばいいのか。田中氏が挙げたのは,日本の産業が持っているデータの価値を,自分たちが作ったAIで“かけ算”することだ。
世界にあるデータの7割以上はWebで検索できないとされているが,その中には企業内のデータも含まれている。開発などで使用するデータなどはもちろんだが,例えば日報なども重要なデータだ。そして日本企業は,こういったデータの保有量が非常に多いのだという。
そのデータをAIでより積極的に活用できれば……というわけなのだが,田中氏が“かけ算”と表現したように,生み出せる価値はAIの精度によって大きく変わってくる。“乗数1”のAIでは,データの価値は変わらないわけだ。
田中氏はより大きな価値を生み出すたために,外部のAIを利用するのではなく,自分たちのAIを作ることを推奨した。
「AIを作る」と聞くと,巨大な費用がかかりそうな印象を受ける。実際,ChatGPTのように,優れた人材と膨大なデータ量,それを処理できる計算資源によって開発された「フロンティアモデル」のAIは,日本ではとても真似できないと田中氏は話した。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / AIを自分たちで作り,新たな産業を創出することが成長への道。さくらインターネットの田中邦裕氏による基調講演をレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250722034/TN/004.jpg) |
だが,田中氏は「軽量モデル」に活路を見いだしている。例えばカスタマーサポートや文章の要約と言った作業に大きなモデルは不要で,必ずしも多言語に対応させる必要はないと話した。
もちろん目的に合ったAIであることが大前提で,場合によってはフロンティアモデルの利用も必要になるだろうが,自分たちの目的に合った軽量モデルAIを作れれば,最適とは言えない規模の外部AIを利用して課金されるようなことはなくなるというわけだ。
そして,大きな価値を生み出すためには,AIをコストダウンの目的だけではなく,新たな事業を創出するために使うことも重要となる。田中氏は,JR西日本がAIエンジニアを招き入れて設立した企業,TRAILBLAZERが,カスタマーサポートや保線のデータなどを学習したAIでグループ各社の作業を効率化しただけでなく,そのソリューションを販売し,さらには顧客から渡されたデータをまとめて戦略を練るといった事業にまで進出していることを挙げた。
「DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質も,コストダウンではなく,新しい産業を作ることだった」と田中氏は話す。AIの活用法とは,ゲーム業界で言えば絵をAIで生成してクリエイターを減らすことではなく,例えばクリエイターが作れる絵をどんどん増やし,1人1人のプレイヤーごとにカスタマイズすることを目指すようなものだと説明した。そういった「体験の個別化」が,長くプレイされることにつながると考えているという。
講演の最後に田中氏は,さくらインターネット単体ではなく,業界全体として成長産業をいかにして作るべきかについて,自身の考えを話した。
近年の日本はインバウンド需要が高まっており,2024年の旅行収支(日本人の海外旅行における支出と,訪日外国人旅行者の日本国内における支出の差額)は6兆円超の黒字となったが,実はそれと同じぐらいの額がデジタル赤字になっている。日本では国外のデジタルサービスが積極的に利用される一方で,海外では日本のデジタルサービスが利用されていないというわけだ。そして,デジタル赤字は2030年から2040年ごろに30兆円に達すると見込まれているという。
デジタル赤字の内訳はインフラや広告などさまざまだが,田中氏はとくにコンテンツサービスに注目している。なぜ豊富なコンテンツを持っていて,デジタル産業も強かったはずの日本が,これほどまでのデジタル赤字を抱えるようになったのか。
田中氏はその要因が,1985年の法律改正によってソフトウェアに著作権が認められた後の企業の動きにあると考えている。法律改正によってソフトウェアそのもので利益を出そうとした企業は大きく成長したが,多くの企業がハードウェアの販売や「人を人月で出す」商売を選択してしまった。それが現在のデジタル赤字につながっているという。
田中氏は「外資系の会社さんが悪いわけじゃない」「便利な海外のサービスが自由に使える国であるべきだと強く主張します」と前置きしつつ,「日本がクリエイティビティを上げ,日本国内と海外で使われるようにしていくことが重要」と話し,生成AIがそのチャンスになり得ると呼びかけた。
その実現のためには,いかにして投資を呼び込むかが重要になる。田中氏は,日本のGDPが約600兆円なのに対し,個人保有の金融資産が2000兆円を超えている実情などを挙げて「日本は少なくともお金がない国ではない」と話し,使われていないお金を市場に流すことが,個々の豊かさにもつながると主張した。
そして,投資を呼び込むためには,投資をしたくなるストーリーが必要だと指摘し,AIがそれに寄与するとアピール。「新しい産業,新しいインフラ,新しいクリエイティビティに資本家がどんどんお金を出して,一人一人が豊かになるような成長産業を作れるよう努力したい」と講演をまとめた。
CEDEC 公式サイト
4Gamer「CEDEC 2025」記事一覧
- 関連タイトル:
 講演/シンポジウム
講演/シンポジウム - この記事のURL:


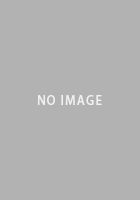
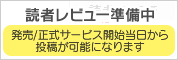
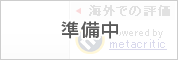






![AIを自分たちで作り,新たな産業を創出することが成長への道。さくらインターネットの田中邦裕氏による基調講演をレポート[CEDEC 2025]](/games/991/G999104/20250722034/TN/005.jpg)